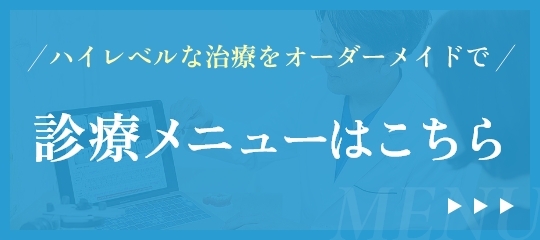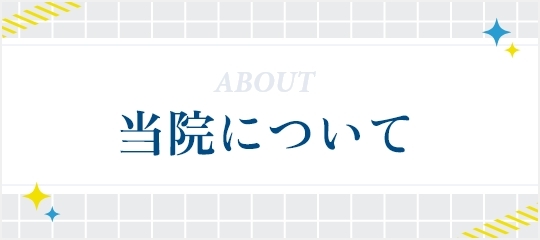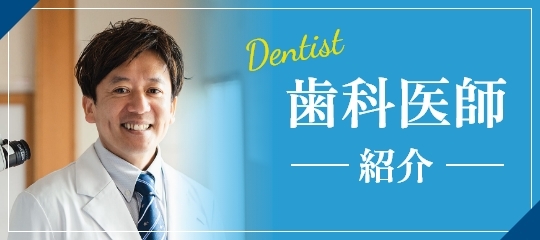20代で歯の神経を抜くのは早い?抜く理由とリスクを歯科医師が解説
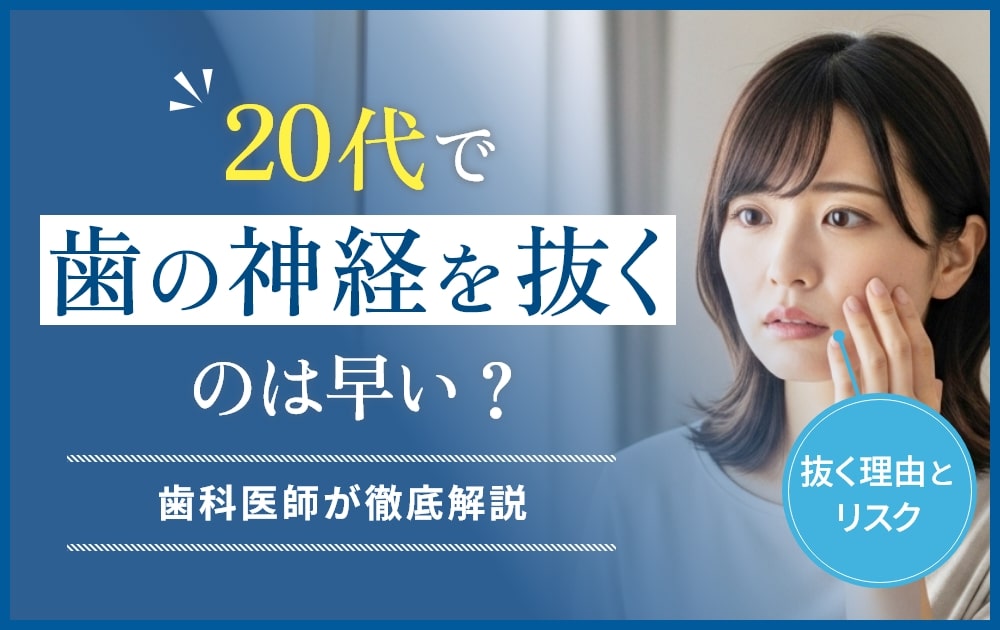
「まだ20代なのに、歯の神経を抜くって言われた…」そんなふうに不安を感じていませんか?
実は、虫歯の進行だけでなく、歯ぎしりやケガ、詰め物の劣化などが原因で、若い世代でも神経に炎症が起こることがあります。神経を抜く治療は、歯を残すための最終手段です。ただ、その後のケアや予防を意識しないと、歯が弱くなったり、再治療が必要になるケースもあります。
本記事では、20代で神経を抜く主な理由や治療の流れ、神経をできるだけ残す・再生する選択肢まで、歯科医師の視点でわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、これからの歯を守るための冷静な判断がしやすくなります。
目次
20代で歯の神経を抜く前に知っておきたいこと

20代で「神経を抜く」と言われると、将来への影響が気になって不安になる方も多いはずです。神経を抜く治療の基本や、若い世代で起こりやすい背景、そして治療が必要かどうかを見極めるポイントをわかりやすく整理しました。
歯の神経を抜く治療とは
歯の神経(歯髄)は、痛みや温度を感じるだけでなく、歯に栄養を届ける重要な組織です。虫歯やケガによって細菌が神経にまで達すると、炎症や強い痛みが続くケースがあり、その場合は根管治療(抜髄)が行われます。
治療の目的は、細菌をしっかり除去して歯を残すことです。具体的には、感染した部分を取り除いたあと根の中を洗浄・成形し、薬剤で密閉、被せ物でふたをする、という流れが一般的です。
歯の神経の治療については、こちらの記事でも解説しています。ぜひご覧ください。

20代でも神経を抜くことがある理由
「若いのに?」と思うかもしれませんが、20代でも神経を抜くケースは珍しくありません。例えば、虫歯が深く進んでいたり、昔の詰め物が劣化して隙間から細菌が入り込んでいたり、日常的な歯ぎしり・食いしばり、スポーツや事故による外傷など、さまざまな原因が考えられます。
また、初期の虫歯は痛みなどの自覚がほとんどないため、気づいたときには神経に近いところまで進行していることもあるのです。生活習慣の乱れや糖分のとりすぎ、口呼吸などもリスクを高める要因です。
早い段階でレントゲンやCTなどの検査を受けると、神経を残せるかどうかを含め、治療の選択肢を整理しやすくなります。早期の受診は、体への負担や費用を減らすことにもつながるでしょう。
神経を抜く判断
神経を抜くかどうかの判断は、虫歯の進行度・症状の強さ・画像検査の結果を組み合わせて行われます。例えば、虫歯がエナメル質や浅い象牙質の段階(CO〜C1)なら、再石灰化による自然修復や経過観察が選ばれることが多いです。
一方で、虫歯が深く進んでいる(C2以上)場合や、自発的な痛み・熱いものでしみる、根の先に病変が見える、膿や腫れがあるといった症状が見られると、抜髄(神経を抜く処置)や根管治療が必要になる場合もあります。
こうした判断は、見た目だけではわからないことも多く、専門的な検査によって原因と状態を正確に把握するのが大切です。それが再発の予防にもつながり、納得のいく治療選択にもつながります。
神経を抜く必要があるサインと症状

神経を抜くかどうかの判断は、痛みの種類や強さ、違和感の出方などが重要な手がかりになります。20代の方にも起こりやすい神経を抜く可能性がある症状を見ていきましょう。
冷たい・温かいもので痛む
冷たい飲み物や温かい食べ物がしみたり、痛んだりするのは、歯の神経(歯髄)に炎症が起き始めているサインです。初期のうちは、刺激があるときだけ痛みますが、進行すると何もしていないのにズキズキと痛みが続くようになります。
これは歯髄炎と呼ばれる状態で、放っておくと神経が壊死し、細菌が根の先まで広がるリスクがあります。早めに歯科を受診すれば、神経を残せる生活歯髄療法という治療が可能な場合もあるため、違和感があれば早めの相談がおすすめです。
ズキズキする痛みが夜間も続く
「夜になるとズキズキ痛んで寝つけない…」そんな症状が出ているときは、炎症がかなり進んでいるサインです。血流が増える夜間は痛みが強く出やすく、神経が限界に近づいている状態と考えられます。
痛み止めで一時的に楽になっても、根本的な原因は解決していません。細菌感染が広がるリスクもあるため、放置は禁物です。この段階になると、神経を抜いて感染源を取り除く抜髄処置が必要になるケースがほとんどです。
噛んだときの痛みや歯ぐきの腫れ
噛むと痛みがある、歯ぐきがぷくっと腫れている、といった症状が出ている場合は、根の先に膿がたまっている可能性があります。炎症が歯の内部からあごの骨にまで広がると、根尖性歯周炎と呼ばれる状態になり、歯ぐきに膿の出口(サイナストラクト)ができることがあります。
このまま放っておくと、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯を抜かざるを得なくなるリスクもあるのです。違和感を覚えたら、できるだけ早く受診し、レントゲンやCTで根の状態をチェックしてもらいましょう。
痛みや症状を放置するリスクについて、以下記事も参考にしてみてください。
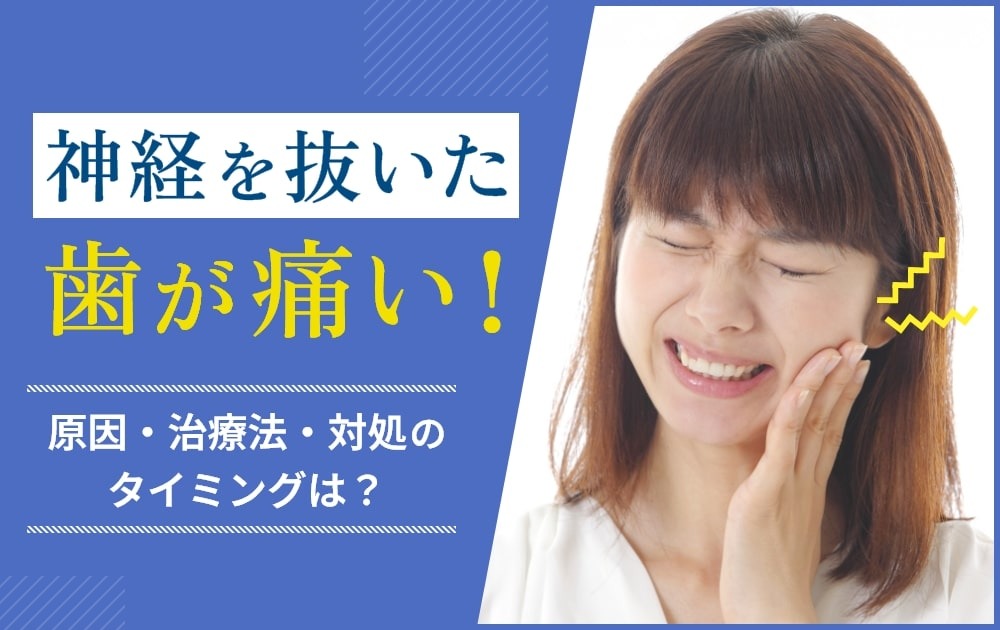
歯の神経を抜いた後に起こるリスクと注意点

神経を抜くと痛みはなくなりますが、その分、歯の構造や働きにいくつかの変化が起こります。特に20代の方にとっては、これから先も長く歯を使っていくため、治療後のケアがとても大切です。神経を抜いたあとの主なリスクと、歯を長持ちさせるための注意点をまとめました。
歯が脆くなる
神経を抜いた歯は、内部に栄養が届かなくなることで乾燥し、しなやかさを失います。その結果、脆くなって割れやすくなるのが大きな特徴です。さらに、治療の際に歯を削るため、全体の厚みが薄くなることもリスクを高める原因の一つです。
硬いものを噛んだときに歯が欠けたり、根元から割れてしまうと、最悪の場合は抜歯が必要になることもあります。これを防ぐには、治療後に強度と密閉性を兼ね備えたクラウン(被せ物)でしっかり補強するのが重要です。噛み合わせの調整や定期的なチェックも、歯の寿命を延ばすポイントになります。
歯の変色や感覚の鈍化
神経を抜いた歯は、時間とともに少しずつ黒ずんで見えることがあります。これは歯の内部に残った血液や神経の成分が影響して変色していくためです。また、神経がないことで痛みや温度を感じにくくなり、虫歯ができても気づきにくくなるケースもあります。
こうした見た目の変化が気になるときは、歯の中から漂白する方法や、セラミックのクラウンで自然な見た目に整えるのも可能です。治療後は、色の変化や違和感がないかを意識し、少しでも気になることがあれば早めに歯科を受診するようにしましょう。
再感染・再治療
神経を抜いた歯は、内部が再び細菌に感染しやすくなっています。例えば、根の中が完全に密閉されていなかったり、被せ物に隙間ができたりすると、そこから細菌が入り込んで炎症や痛みを引き起こすことがあります。
再治療を防ぐためには、根の中をしっかり殺菌し、隙間のない状態で封鎖することがとても大切です。特に自由診療で行われる精密根管治療では、マイクロスコープやラバーダムといった専用機器を使って、再感染のリスクを大きく減らせます。
神経を残す・再生する治療の可能性
最近では、神経を抜くだけでなく、できるだけ残す、あるいは再生を目指す治療法も進化しています。特に20代のようにこれから長く歯を使っていく世代にとって、神経を残せるかどうかは大きな意味を持ちます。知っておきたい保存療法と再生医療の選択肢について見ていきましょう。
生活歯髄療法などの保存療法
生活歯髄療法は、神経の一部を残して自然治癒を促す治療法で、感染がごく一部にとどまっている場合に選択されます。中でもよく使われているのが、殺菌力と密閉性に優れたMTAセメントを使うMTA覆髄法です。細菌の侵入を防ぎつつ、神経の自己回復をサポートする方法となります。
この治療を成功させるには、感染の取り残しを防ぐために精密な操作が必要で、マイクロスコープやラバーダムといった専用の機器も不可欠です。だからこそ、早めに受診して状態を正確に診断することが、神経を守るチャンスになります。
歯髄(歯の神経)再生治療
歯髄再生治療は、失われた神経を再生させる新しい治療法です。感染した歯の中を丁寧に清掃・消毒したあと、不用歯(親知らずなど)から採取した歯髄幹細胞や再生を促す薬剤を使って、歯髄(神経組織)の再構築を目指します。前歯の細菌感染の程度が低い(膿が小さい)方に特に向いていますが、臼歯の感染した根にも行うことが出来ます。
この治療は、自分の歯を少しでも長く残したい、将来の歯の健康を大切にしたいと考える方に向いています。
歯髄再生治療について以下記事でも解説していますので、あわせてごらんください。
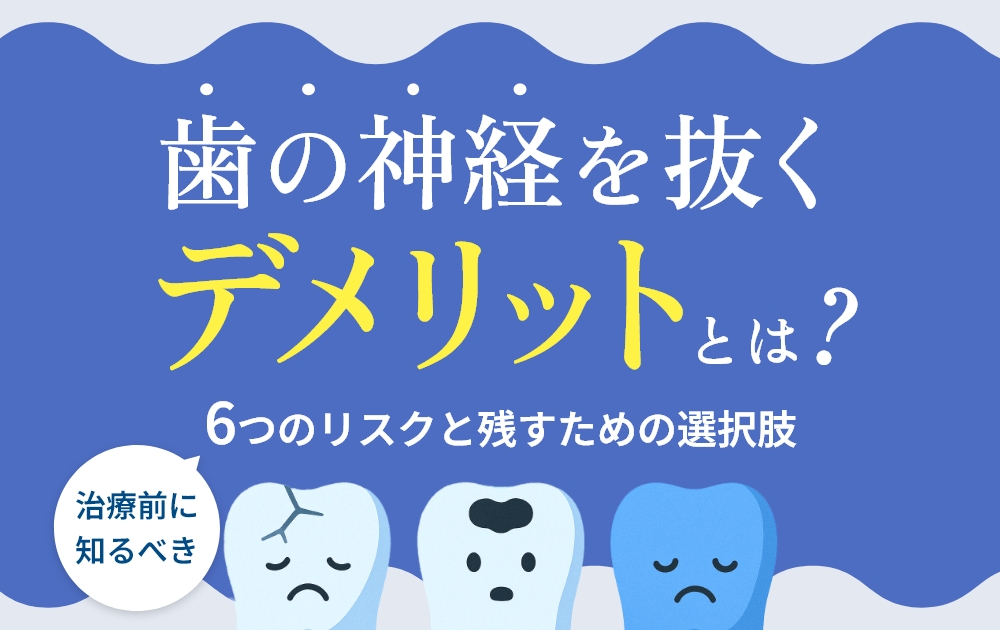
ライフスタイルに合わせた
最適な治療法を提示いたします。
神経を残すか抜くかの判断基準
神経を残せるかどうかは、痛みの強さ、感染の広がり具合、そしてレントゲンやCTなどの画像検査の結果をもとに総合的に判断されます。「とにかく残したい」と無理をすると、かえって炎症が慢性化したり、再治療が必要になるリスクもあるため注意が必要です。
大切なのは、歯の将来的な寿命を第一に考えることです。信頼できる歯科医師のもとで、自分の歯の状態や治療の選択肢をしっかり理解しておくと安心です。
神経を抜く治療の流れと再発を防ぐポイント

神経を抜く根管治療は、歯の内部に入り込んだ細菌を取り除き、再感染を防ぐためのとても繊細な治療です。治療の基本的な流れと再発を防ぐための精密な対策について紹介します。
根管治療の流れ
根管治療では、感染した神経を取り除いたあと、歯の中をしっかり洗浄・消毒し、細菌が再び入らないように密閉します。
一般的なステップは以下のとおりです。
- 虫歯の除去
- 感染した神経の除去
- 根管内部の洗浄と形を整える処置
- 消毒薬による殺菌
- 根の中に薬剤を詰める(根管充填)
- 被せ物でふたをして密閉
治療にかかる回数は症例によって異なりますが、2〜5回程度が一般的です。一つひとつの工程を丁寧に進めること、そして衛生管理の徹底が、治療の成功を左右します。
精密根管治療で再発を防ぐ仕組み
再感染を防ぐには、根管の中に残った細菌をどれだけ確実に取り除けるかが大切なポイントです。自由診療で行われる精密根管治療では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使い、肉眼では見えない細かな部分までしっかり確認しながら治療を進めます。さらに、ラバーダムと呼ばれるゴムのシートで歯のまわりを覆い、唾液の混入を防止します。
治療には柔軟性と耐久性のあるNi-Tiファイル(ニッケルチタン製の器具)を使って、根管の形状に合わせた精密な洗浄・成形を行います。こうした設備と技術を組み合わせることで、根の中の再感染リスクを最小限に抑えられるのです。
被せ物の素材と寿命の違い
治療後に装着する被せ物(クラウン)は、歯を守るうえでとても重要な役割を担っています。素材によって見た目や耐久性、再感染への強さに違いがあります。
例えば、保険診療でよく使われる銀歯はコストを抑えられる反面、密閉性やフィット感には限界があります。一方、セラミックやジルコニアといった自由診療の素材は、歯になじみやすく、劣化しにくいのが特徴です。見た目も自然で、長期間きれいな状態を保ちやすい点が魅力です。
素材を選ぶときは、見た目だけでなく、耐久性や機能面、将来的なトラブルのリスクまで含めて考えましょう。
関口歯科の根管治療の特徴

歯の神経を抜いたあとも、できるだけ長く健康な状態を保つためには、治療の精度がとても重要です。
埼玉県川越市にある関口歯科では、すべての根管治療を自由診療で行い、再発を防ぐための精密な体制を整えています。当院の根管治療の取り組みをご紹介します。
完全自由診療による精密根管治療の体制
関口歯科では、根管治療のすべてを自由診療で提供しているのが大きな特徴です。マイクロスコープや歯科用CT、Ni-Tiファイル、ラバーダムなどの先進的な設備を組み合わせることで、肉眼では見えない細かい根管の分岐や感染部分までしっかり対応します。
治療の質を最優先に考え、時間や材料に制限をかけずに一つひとつの症例に丁寧に向き合っています。目に見えない部分の精度こそが、歯の寿命を左右すると考え、見逃しのない診療体制を徹底しています。
院長による丁寧な診査とカウンセリング
治療を受ける前に不安や疑問があるのは当然のことです。関口歯科では、院長がカウンセリングを直接担当し、患者さまの症状だけでなく生活習慣やお悩みまで丁寧にヒアリングしています。
診査では、CT画像やマイクロスコープを使って根の状態を細かくチェックし、わかりやすく説明します。神経を残す治療法や再生治療など、可能な選択肢を提示したうえで、納得して治療を選んでもらうことを大切にしています。
再発防止のための徹底管理体制
根管治療で最も重要なのは、治療後に再発させないことです。関口歯科では、治療ごとに器具の滅菌を徹底し、根の中の密閉性を高める体制を整えています。
治療後も定期的に経過をチェックし、レントゲンやCTで内部の状態を確認します。さらに、被せ物のフィット感や咬み合わせのバランスまで一貫して管理することで、長く安定した状態を維持しやすくしています。
こうした丁寧なフォローが、再治療のリスクを大きく下げるポイントとなるのです。
関口歯科の特徴や治療について、詳しくは関口歯科の公式ホームページをご覧ください。

ライフスタイルに合わせた
最適な治療法を提示いたします。
神経を抜いた後の歯を長持ちさせるケア

神経を抜いた歯は、痛みが出にくくなるぶん、知らないうちにトラブルが進行してしまうことがあります。治療後の歯をできるだけ長く健康に保つために大切なセルフケアと定期メンテナンスについてまとめました。
抜髄後に必要なホームケア
神経を抜いた歯は、再感染や破折のリスクがあるため、日々のセルフケアが欠かせません。
歯磨きの際は、歯と歯ぐきの境目をやさしく丁寧に磨き、フッ素入りの歯磨き剤で再石灰化を促すのが効果的です。歯間ブラシやデンタルフロスを併用して、歯と歯の間の汚れもきちんと除去しましょう。
また、咬む力が片側に偏らないよう注意し、食いしばりや歯ぎしりのある方はナイトガードの使用も検討すると安心です。
定期メンテナンスの重要性
セルフケアだけでなく、歯科医院での定期的なメンテナンスも欠かせません。3〜6ヶ月に一度の通院で、被せ物の状態、歯ぐきや咬み合わせのチェックを行い、必要があれば調整を行います。
また、歯科医院では専用の機器を使ったクリーニングで、家庭では取りきれない汚れやバイオフィルムをしっかり除去できます。
治療した歯の見た目が変わっていなくても、内部で異常が進行していることもあるため、定期的にレントゲンで確認しておくことも重要です。
再治療が必要なサインを見分ける
治療が終わったあとでも、「なんとなく違和感がある」「噛むと痛い」「歯ぐきがぷくっと膨れている」といった症状があれば、要注意です。こうしたサインは、根管内部の再感染や、封鎖の不備、歯根のひび割れなどが原因となっている可能性があります。
放っておくと症状が悪化し、歯を残せないケースもあるため、少しでも異変を感じたら早めに受診しましょう。早期に再治療を行えば、歯を守れる可能性が高まります。
20代が歯の神経を抜くときによくある質問
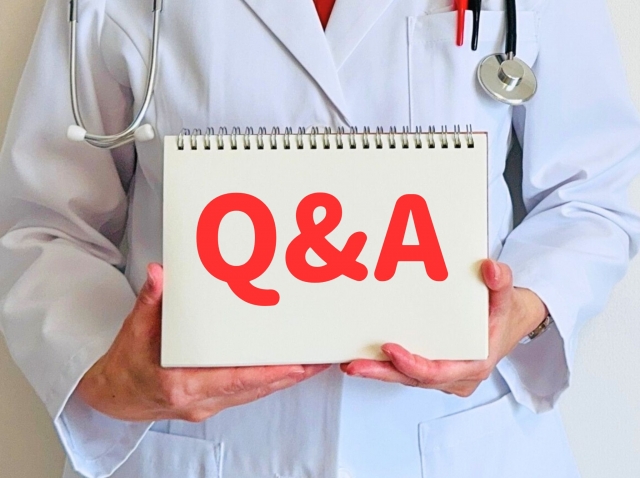
20代で歯の神経を抜くとなると、将来への不安や治療の影響が気になる方も多いのではないでしょうか。よくある疑問に歯科医師の視点からわかりやすくお答えします。
20代で神経を抜いても将来大丈夫?
20代で神経を抜くと、「この先大丈夫かな?」と不安に思う方も多いかもしれませんが、きちんと治療とケアを続けていけば、長く使い続けることは十分に可能です。
神経を抜いた歯はどうしても脆くなりやすいため、被せ物での補強や咬み合わせの管理が欠かせません。さらに、早期の受診と予防ケアを習慣化することで、再感染のリスクを下げられます。
適切な処置を行えば、将来的にも問題なく歯の機能を保てます。
神経を抜いた歯の寿命はどのくらい?
神経を抜いた歯の平均寿命はおよそ10年以上とされていますが、実際には治療の精度やその後のケアによって大きく差が出ます。
再感染を防ぐための精密な根管治療を受けたうえで、定期的に状態をチェックし、被せ物の密着や咬み合わせを適切に管理できれば、さらに長期間機能を保てる可能性があります。寿命をのばすには、見えない部分まで含めた丁寧なケアが重要です。
神経を抜いた後の痛みはどれくらい続く?
神経を抜いたあとは、通常2〜3日から長くても1週間程度で痛みや違和感が落ち着くケースがほとんどです。これは、神経を除去したことで歯の周囲に炎症が一時的に起きているためで、自然に回復していく傾向があります。
ただし、痛みや腫れが強く続く場合は、炎症が残っていたり、再感染の可能性もあるため、我慢せずに早めの受診をおすすめします。
神経を抜いた後も痛みがあるのはなぜ?
治療後もしばらく痛みが残るときには、根の先に炎症が残っている、噛み合わせの力が強くかかっている、あるいは再感染が起きているなど、いくつかの原因が考えられます。
違和感や痛みが続くときは、レントゲンやCTなどで歯の内部を詳しく確認し、必要に応じて再治療を行います。そのまま放置すると悪化するおそれもあるため、早めの対応が大切です。
治療期間はどのくらいかかる?
根管治療にかかる期間は、感染の広がり方や歯の構造によって異なりますが、一般的には2〜5回の通院で終了し、全体で2〜8週間ほどを見込むのが目安です。被せ物の作製にも時間がかかるため、治療計画は余裕を持って立てるのがおすすめです。
歯髄再生治療はどんな人に向いている?
歯髄再生治療は、前歯の細菌感染の程度が低い(膿が小さい)方に特に向いていますが、臼歯の感染した根にも行うことが出来ます。「できるだけ歯を抜かずに残したい」「将来にわたって自分の歯を使い続けたい」と考える方には、特に選択肢となる治療法です。
ただし、再生治療が可能かどうかは歯の状態によって変わるため、精密な診査が必要です。気になる場合は、まず歯科医院でレントゲンやCTなどの検査を受けて、自分の歯に適した治療法を相談してみましょう。
20代で神経を抜くか迷ったら、関口歯科へ相談を

「本当に神経を抜くしかないの?」「将来この歯は持つのかな?」と不安になる方も少なくありません。
しかし、正確な診断と精度の高い治療を受けることで、歯を長く残すことは十分に可能です。
川越市の関口歯科では、マイクロスコープやCTを活用した精密根管治療をはじめ、神経を再生する先進的な歯髄再生治療にも対応しています。どちらの治療も自由診療で行い、再発を防ぎながら歯の寿命を延ばすことを大切にしています。
「抜くしかないと言われたけど、迷っている」という方も、一度ご相談ください。あなたの大切な歯を守るために、ベストな選択肢を一緒に考えていきましょう。
ライフスタイルに合わせた
最適な治療法を提示いたします。
-
日本歯科大学歯学部
-
丸山歯科クリニック(渋谷区)
-
四谷三丁目歯科矯正歯科(新宿区)
-
Academy of Microscope Enhanced Dentistry(アメリカ顕微鏡歯科学会)認定医
-
日本顕微鏡歯科学会 認定医
-
日本歯周病学会 認定医
-
日本有床義歯(入れ歯)学会 認定医
-
BPSデンチャー(総義歯)クリニカルデンティスト
-
臨床歯科を語る会
-
F会
もっと見る